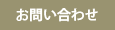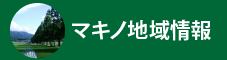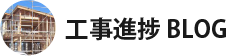昨日に続き障子のこと
昔は、建具1枚貼りの紙はもちろんのこと、ロールの障子紙もありません。長方形の大きさのものばかりです。
ですから、お寺や茶室などでもちゃんと文化財として配慮されている建物の障子は、縦にも横にも障子の継ぎ目が出来る長方形の昔ながらの障子紙の規格の大きさのものが貼られています。
障子の建具の材質は、数寄屋や茶室などの場合はやわらかい感じの赤杉(杉の赤身の部分の良材)、桧などの白木の造作の場合は、現在では米ヒバ(イエローシーダー)の大木の木目の細かい良材の部分が主に使われるのではないかと思います。
障子の用語いろいろ(思いつくままに)
摺り上げ障子(すりあげしょうじ)-障子の下半分の部分が可動になっていて、全て障子になる場合と、下の部分が障子を摺り上げてガラスになり、外の景色が楽しめるようになっている建具。この摺り上げの部分、ばねも何もなく木の摩擦だけでもたしている、建具屋さんの技術が光るところ。雪見障子という場合もある。
水腰障子(みなこししょうじ)-障子の下の部分に腰板が入らず、一番下から障子紙になっている建具。近代建築家(吉田五十八や谷口吉郎)などの和風の建物の作品に良く用いられて広まったもののように思う。
猫間障子(ねこましょうじ)-障子の真ん中の辺りにガラス部分が小さく入った障子、少し昔の映画やテレビの庶民の住宅の茶の間などによくあります。
縦框(たてかまち)横框(よこかまち)-障子の枠材をこう称する。建具の外周四辺の縦の部分を縦框、横の部分を横框という。縦框は見付一寸、横框は上が1寸~1寸2分、下は窓の場合は1寸5分、出入口の場合は2寸位が標準かと思っています。
桝子(ますこ)-正方形の桟の組み方
縦繁(たてしげ)・横繁(よこしげ)-縦桟の間隔が短いものを縦繁、横桟の間隔が短いものを横繁という。
吹寄せ-2本又は3本一まとまりの桟が等間隔で並んでいる様子。
建築用語も細かい所まで色々名前が付いています。知れば知るだけ面白さも増してくるものだと思います。
ブログランキング、ポチッと一つお願いします。![]()
![]()
ほんだ建築トップページへはこちらから